
菊花賞当日の5レースに行なわれる新馬戦は、後のGI馬を多数輩出してきた出世レース。改めて、その実績を振り返ってみる。
- 2020年 1着シャフリヤール:ダービー
- 2018年 1着ワールドプレミア:菊花賞、天皇賞・春
- 2013年 1着トーセンスターダム:豪・GIトゥーラックH、エミレーツS
- 2012年 1着エピファネイア:菊花賞、ジャパンカップ
- 2009年 1着ローズキングダム:朝日杯フューチュリティS、ジャパンカップ、2着ヴィクトワールピサ・・・皐月賞、有馬記念、ドバイワールドカップ
- 2008年 1着アンライバルド:皐月賞、3着ブエナビスタ:阪神JF、桜花賞、オークス、ヴィクトリアマイル、天皇賞・秋、ジャパンカップ、4着スリーロールス:菊花賞
重賞勝ち馬やGI2着馬も挙げだすときりがないため、GIを勝った馬に限定したが、それでもこの新馬戦がいかに出世レースであるかは一目瞭然だろう。特に、2008年のレースからはGI馬が3頭も誕生し「伝説の新馬戦」と呼ばれている。
ところがここでは"後のGI馬"に限定したため、ブエナビスタ・スリーロールスに先着した馬の名がここにはない。
それが、リーチザクラウンである。

通算成績は26戦4勝。そのうち重賞は2勝。菊花賞までは世代のトップクラスに位置していたものの、その後は苦戦の連続で、4歳春に制したマイラーズC以降は13戦未勝利と、GIを勝てないまま現役を退いた。新馬戦で先着したとはいえ、GIを6勝して歴史的名牝となったブエナビスタに比べれば、その戦績は見劣りすると言わざるを得ない。
しかし、その存在感は同期のGI馬たちに勝るとも劣らないほど大きく、引退から10年が経とうとしている現在も変わらないと思うのは、決して私だけではないはずだ。
青鹿毛ながら黒光りする雄大な馬体。ライバルたちを引き連れて逃げる姿。代名詞にもなった激しい気性。通算成績だけ見ればいわば"脇役"だったとしても、なぜかその存在感は非常に大きく、馬名から連想されるとおり高貴で、時に崇高ですらあった──。
2006年2月5日。リーチザクラウンは、社台ファームに生を受けた。父は、1998年のダービーなどGIを4勝したスペシャルウィーク。母のクラウンピースは現役時6戦1勝だったが、4代母のクリスエヴァートはニューヨーク牝馬三冠を達成し、祖母クラシッククラウンも米国のGIを2勝していた。その全兄チーフズクラウンは、米国のGIを8勝し、種牡馬としても数々の名馬を輩出している。
さらに、5代母ミスカーミーを起点とする他の一族からは、ダービー馬のディープスカイや、宝塚記念とジャパンカップを制したタップダンスシチー。そして、牝馬ながらケンタッキーダービーを制覇したウイニングカラーズなどが誕生している。リーチザクラウンが纏う高貴な雰囲気は、活躍馬が続出する超名門の血統からきているのかもしれない。
父母ともに所有していた臼田浩義氏の持ち馬となり、栗東の橋口弘次郞厩舎に入厩したリーチザクラウンは、10月26日にデビューを迎えた。それが、冒頭に記した「伝説の新馬戦」である。
このとき、パドックに登場したリーチザクラウンの馬体重は520kg。1番人気の座こそ、同じく父がスペシャルウィークであり母もGI馬ビワハイジというブエナビスタに譲ったものの、その馬格は2歳馬と思えないほど雄大だった。3番人気のアンライバルドが478kgだったこともあり、リーチザクラウンの存在感は早くも際立っていた。ただ、レースの結果を左右したのは、それぞれがこの時点で持ち合わせていたセンスの差だったのかもしれない。
ゲートが開くと、やや出遅れたブエナビスタが後方を追走する一方で、五分のスタートを切ったアンライバルドは4番手。リーチザクラウンは8番手でレースを進めた。新馬戦らしくスローペースとなり、前にいる馬には有利な展開。直線に入ると、すぐにアンライバルドが抜け出し、それをリーチザクラウンとブエナビスタが懸命に追った。しかし、馬体を併せるまでには至らず、アンライバルドが1馬身4分の1差で快勝。リーチザクラウンも、ブエナビスタの猛追を押さえたものの、初戦は2着に終わった。
このレースが「伝説の新馬戦」と呼ばれるのはまだ先のこと。ただ、メンバーレベルの高さが証明されるのに、ほとんど時間はかからなかった。
まず、リーチザクラウンは、武豊騎手を鞍上に配し中2週で未勝利戦に出走。初戦から一転して、今度は逃げの手に出た。すると、勝負所はおろか、直線でも全く追われることなく後続に2秒1の差をつける圧勝。衝撃の初勝利を挙げると、続く千両賞も楽に逃げ切り、あっという間にオープン入りを果たした。

一方のブエナビスタも、リーチザクラウンの初勝利の前日に勝ち上がると、抽選を突破して挑んだ阪神ジュベナイルフィリーズも完勝。新馬戦で3着に敗れた馬が、1ヶ月半で世代最初のGI馬に上り詰めた。
巷では、早くも「10月26日・京都5レースの新馬戦」が噂になり始め、そこで2歳女王に先着していたリーチザクラウンに集まる注目度と存在感は、日増しに大きくなっていた。それだけに、次走のラジオNIKKEI杯2歳Sは、ある意味で衝撃のレースとなる。
近2走、逃げて楽勝したリーチザクラウンは、単勝1.3倍の圧倒的な支持を集めたが、このレースでまた1頭、後に自らの運命を大きく左右するライバルとの出会いがあった。
ロジユニヴァースである。

アンライバルドと同じネオユニヴァースの初年度産駒で、関東馬ながら7月阪神の新馬戦を快勝したロジユニヴァースは、続く札幌2歳Sも連勝。一足早くクラシック候補に名乗りを上げていた。ただ、2戦とも大きな着差をつけたわけではなく、明らかに楽々と勝ってきたリーチザクラウンに1番人気の座を譲っていた。
レースは、この日も逃げたリーチザクラウンを、ロジユニヴァースが2番手から追う展開。向正面で、2頭と3番手以下の差は5馬身に広がり、続く3~4コーナー中間で、リーチザクラウンはロジユニヴァースとの差も広げにかかる。一方のロジユニヴァースは、ここで3番手集団に吸収され、2頭の決着はあっけなくついたかに思われた。
ところが、直線に入るとロジユニヴァースはすぐに盛り返し、残り300mでリーチザクラウンに並びかけた。すると、今度はリーチザクラウンが苦しくなって抵抗できず、坂の途中からはどんどんと差が開いてしまう。
最後は完全に末脚をなくし2着を確保するのが精一杯で、4馬身差をつけられる完敗。楽に連勝していたリーチザクラウンが関東の刺客に大きく引き離されて敗れたシーンは、関西の競馬ファンにとってはショッキングな場面だったことだろう。

それでも、リーチザクラウンには良い意味での鈍感力が備わっていたのか──この敗戦を引きずるようなことはなかった。
年明け初戦となるきさらぎ賞は、2勝馬こそ複数いたものの、重賞の連対実績がある馬は自身だけというメンバー構成。またしても断然の支持を集めると、今度は楽々と逃げ切り、父と同じレースで重賞初制覇を達成した。その勝ちっぷりで再び存在感を高めることに成功し、そのまま皐月賞に直行した。
そして2ヶ月後……。その大舞台で待ち受けていたのは、ラジオNIKKEI杯2歳S後に弥生賞も勝利し、デビューからの連勝を4に伸ばしたロジユニヴァース。そして、あの新馬戦後に京都2歳Sの3着を挟んで、若駒SとスプリングSを連勝したアンライバルドだった。
単勝10倍を切ったのは、この3頭のみ。4番人気のセイウンワンダーは20倍を超え、完全な「三強」の図式で、スタートを迎えた。
ゲートが開くと、大外枠から逃げられなかったリーチザクラウンは、5番手に位置した。しかし、終始馬場の外目を回らされた上に、これまでとは一変して、GIらしく淀みのない流れ。先行各馬にとっては、息の入らない厳しい展開になってしまう。
それでも4コーナーで先頭に並びかけ"さあ、これから"と思った矢先。一気にまくってきたアンライバルドにかわされるとリーチザクラウンは全く抵抗できずに後退し、連対はおろか、初めて掲示板を外す13着に大敗した。それは、リーチザクラウンが明確に味わう初めての屈辱と挫折で、同世代での立ち位置が大きく揺らいだ瞬間だった。
そのため、1ヶ月半後に迎えた大一番のダービーは、皐月賞の雪辱を果たす舞台にもなった。ここまで2着3回と、あと一歩のところまで何度も迫っていた橋口調教師にとって悲願のレース。さらにはスペシャルウィークとの父仔制覇や、オーナーの臼田氏にとってはそれ以来のダービー制覇など、様々な記録や悲願がかかる一戦だった。
ダービー当日は、午後からゲリラ豪雨のような大雨に見舞われた。不良馬場でのダービーは実に40年ぶり。しかし、持久力タイプのリーチザクラウンには恵みの雨となるはずで、前回の大敗により5番人気と評価を下げていたものの、様々な悲願が叶う環境は着々と整いはじめていた。
レースは、ジョーカプチーノが大逃げ。前半1000m通過は59秒9と、馬場を考えればかなりのハイペースだった。リーチザクラウンは、そこから10馬身ほど離れた2番手を追走。単騎逃げのようなかたちで、馬場を考えれば絶好の位置だった。一方、こちらも皐月賞で人気を裏切り、14着と大敗していたロジユニヴァースは、そこから3馬身差の3番手。そして、今回1番人気に推されていたアンライバルドは、後方12番手に控えていた。
その後、リーチザクラウンは4コーナーでジョーカプチーノと入れ替わると、早くも先頭に立って後続との差を広げにかかる。アンライバルドや他の有力馬は、馬場に脚をとられて伸びあぐね、王座戴冠の瞬間は目の前に迫っていたが、同じ思いを抱えながら、内ラチ沿いを一気に伸びる馬がいた。
──ロジユニヴァースだった。
ラジオNIKKEI杯と同じく、残り300mで先頭に立つと、今度はリーチザクラウンも必死に抵抗。しかし、一度広げられた2馬身の差は挽回できそうでできず、ついには、ゴール前でその差をさらに広げられてしまう。
結果、皐月賞大敗から世紀の大逆転劇、そして悲願を叶えたのはロジユニヴァースだった。一方、完璧なレースをしたリーチザクラウンは、あと一歩のところまで迫るも届かず2着に惜敗。自身を取り巻く、多くの悲願を叶えることはできなかった。
激戦の疲れを癒すため、夏場を休養に充てたリーチザクラウンは、秋の目標を菊花賞に置き、前哨戦の神戸新聞杯に出走。2レースぶりに、逃げの手に出た。結果は、ゴール寸前で上がり馬のイコピコに差されたものの、レコードを誘発する好タイムで最後まで粘り0秒3差の2着。まずまずの内容で、本番に駒を進めた。
本番の菊花賞にアンライバルドは出走したものの、ロジユニヴァースが回避したこともあり、GIで初めて1番人気に推されたリーチザクラウンは、この日もライバルを引き連れて逃げた。スタートしてすぐに引っかかるような仕草を見せたものの、先頭に立つとすぐに折り合い、2番手以下を大きく引き離して快調に飛ばす。
最初の1000mは59秒9で、次の1000mが1分3秒2と理想的なペース配分。さらに、2周目の坂の下りで後続を引きつけるという、長距離で逃げる馬にとってはこれ以上ないレース運びで、春の鬱憤を晴らす準備は十二分に整っていた。
迎えた直線。この時点で、イコピコはまだ後ろから3頭目に位置して抜け出すのに時間がかかり、末脚をなくしたアンライバルドは後退していく。これまでで最大のチャンスを掴んだリーチザクラウンに、それを阻止しようと、後続から迫る差し馬。その中に、ダービーのロジユニヴァースと同じ1枠1番のゼッケンをつける馬がいた。それは、あの新馬戦で一度だけ対戦した見覚えのある馬……。
スリーロールスだった。
新馬戦で、三強に続く4着に好走したスリーロールスは、3戦目で初勝利。しかし、2勝目はそこから5戦を要し、前走で1000万クラス(現・2勝クラス)を勝利した上がり馬だった。このレースでは、8番人気と伏兵の評価ながら、その父は武騎手とともに奇跡の末脚を繰り出して菊花賞を制覇。産駒も、同レースで強さを発揮するダンスインザダークだった。
リーチザクラウンも、その追撃を跳ね返そうと懸命に粘って抵抗。すると、スリーロールスもここにきて苦しくなったのか、一度は馬場の中央まで大きく寄れてしまう。それでも、再び立て直されて伸びると、今度こそリーチザクラウンをかわし、その間隙を突いたフォゲッタブルにもハナ差先着して優勝。
逆転で菊の大輪を掴み取り、このとき既に「伝説の新馬戦」と評されはじめていたあのレースから、また1頭、新たなGI馬が誕生したのだ。
一方、ダービーに続きほぼ完璧なレースを見せながら、最後の最後に力尽きて5着に敗れたリーチザクラウン。世代トップクラスの実力を持ち、間違いなく三冠路線で主役級の役どころを演じながらも、ビッグタイトルには、あと一歩のところで届かなかったのである。
そこから、古馬との戦いに挑んだリーチザクラウン。クラシックでも好走した実績から、引き続き好走が期待されたものの、よもやの苦戦を強いられることになってしまった。
菊花賞の次走に選ばれたのは、1ヶ月後のジャパンC。ここも、強豪古馬を引き連れて堂々とした逃げっぷり。そして、直線半ばまで先頭の座を守って見せ場を作るも、最後失速して9着に敗戦。そして、有馬記念でも同様に逃げを打ったものの、今度は4コーナーで早々に失速し13着。年明け初戦のフェブラリーSも、ダートに適性がなかったか10着に終わってしまう。
そんな中、迎えたのが、4歳シーズンの2戦目マイラーズCだった。ここは、武騎手が負傷療養中のため、安藤勝己騎手が代打での騎乗。2歳時に、同じコースで千両賞を勝って以来、およそ1年4ヶ月ぶりのコンビ復活だった。
このマイラーズCでは、ダービー以来、久々に逃げなかったリーチザクラウン。スタートしてすぐいきたがるような素振りを見せたものの、上手く制御され、3番手からレースを進める。
直線に入ると、父のスペシャルウィークらしい瞬発力はないものの、徐々に──しかし確実に前との差を詰め、坂下でシルポートとタマモナイスプレイをかわし先頭に立った。そこへ、皐月賞で先着を許したトライアンフマーチが内から追い込み接戦となるも、クビ差凌ぎ1着でゴールイン。
これが、きさらぎ賞以来となる実に1年2ヶ月ぶりの勝利となり、古馬に混じっても上位の実力、主役級のレベルにあることを十分に知らしめたのである。
前年の秋以来、再びその存在感を高めたリーチザクラウン。いよいよ戴冠の時も近いかと、周囲の期待や注目も大きくなったが、ここからの競走馬生活は、脚元を含めた自身の体とも戦わなければならなかった。
1番人気に推された安田記念は、前走と同様に好位からレースを進めた。ほんの少し前を追いかけるようなところがあったものの、最内枠を利してインぴったりを回り、折り合いを欠いているようにも見られない。
ところが、3~4コーナー中間から徐々にポジションを下げると、直線では全く伸びず14着と大敗。レース後には骨折が判明し、半年の休養を余儀なくされてしまった。
幸い重度のケガではなく、年内に復帰が叶うと、武騎手とのコンビ復活で挑んだ阪神Cは7着。西山茂行氏にオーナーが変わった年明けの京都金杯は4着で、尻上がりに調子を上げた。
さらに中山記念では、後方待機策から、前年の最優秀3歳牡馬に輝いたヴィクトワールピサに迫り3着を確保。これで復活を印象づけたかと思いきや、マイラーズCは、直線で再三前が詰まって9着に敗戦。続く都大路Sも、3コーナーで躓くアクシデントに見舞われて無理をさせなかったため14着と、なんとももどかしいレースが続いてしまう。
そして、安田記念を大敗して迎えた秋初戦のアイルランドトロフィーは、久々の逃げ。しかも、超のつく大逃げでスタンドを湧かせた。しかし、それは途中から喉が鳴り始めて苦しくなり、いきたがったのが原因だった。それを抑えると馬と喧嘩になるという北村宏司騎手のやむを得ない判断で、これにより、喘鳴症を患っていることが判明。手術が行なわれ、翌年のダービー卿チャレンジトロフィーで戦線に復帰するも全快には至らず……。
その後、4戦した後に生涯2度目の骨折を発症し、復帰戦となった2013年の東京新聞杯でも大敗し、ついにここで競走馬生活にピリオドが打たれたのである。
その後、リーチザクラウンはアロースタッドで種牡馬入りを果たした。GI勝ちの実績はなかったものの、数少ないスペシャルウィークの後継種牡馬として期待され、2月に引退した馬としては多いともいえる53頭に種付け。そこから34頭の産駒が誕生した。
すると、2016年にデビューしたその初年度産駒たちが、いきなり活躍。仕上りが早く、なおかつ勝ち上がり率の高さが特徴。10月からは、社台スタリオンステーションで繋養されることも決定した。社台ファームに生を受けたリーチザクラウンにとっては、ある意味、凱旋の「里帰り」のようなものだったが、この世代の内国産馬で同場に繋養された種牡馬は、2021年現在リーチザクラウンのみ。まさにそれは、快挙といえる里帰りだった。
そして、翌1月にはキョウヘイがシンザン記念を勝利し、産駒初のJRA重賞制覇を達成。さらに、佐賀競馬ではスーパーマックスが重賞を計8勝し、中央のレースにも度々挑戦してチャレンジCで5着に入るなど健闘した。
社台スタリオンステーションに移った2017年、種付け頭数は、実に前年の3倍以上となる98頭にまで増加(2021年からは、再びアロースタッドにて繋養)。同期の中では、再び主役級の存在感を示して見せた。

「伝説の新馬戦」で2着に好走したからではないが、それを巡る不思議な運命に翻弄された2009年のクラシック路線。馬名のとおり「戴冠」することは、ついに叶わなかったものの、リーチザクラウンは間違いなくその中心に存在し、主役級の活躍を見せた。
競走馬生活の晩年はケガや喘鳴症に悩まされ、その存在感は一度しぼみかけたものの、種牡馬となってから、再び輝きを取り戻したといって間違いない。
競馬新聞の馬名欄の片隅に彼の名を見つけたとき、現役時に見せたような大逃げや、惚れ惚れするような馬体を思い出し、つい心躍るようなワクワクした気持ちになってしまうのは私だけだろうか。それは、きっと私の心の中にいるリーチザクラウンの存在が、脇役と呼ぶには似つかわしくないほど大きく、「今頃あいつはどうしているだろうか」と、いつも気になり続けているからだろう。
写真:Horse Memorys

![[重賞回顧]夏を越して走りが洗練されたアーバンシックが菊の大輪を戴冠!~2024年・菊花賞~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_6156-150x150.jpeg)
![[重賞回顧]秋晴れに輝く2つ目のティアラ 盤石の競馬で突き抜けたチェルヴィニアが二冠達成~2024年・秋華賞~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_6015-150x150.jpeg)
![[重賞回顧]古馬相手でも適距離では負けられない! 混戦を断った3歳馬シックスペンスが、秋初戦を快勝~2024年・毎日王冠~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_5746-150x150.jpeg)
![[重賞回顧]春の悔し涙は歓喜の涙に。アクシデントを乗り越えたルガルと西村淳也騎手が、復活のGⅠ初制覇~2024年・スプリンターズS~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2024/09/img_5685-1-150x150.jpg)
![[きさらぎ賞・東京新聞杯]今も駆ける スター"ウマ娘"の血を引く者たち〜日曜重賞編〜](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/04/e3defdd4ecd-300x100.png)




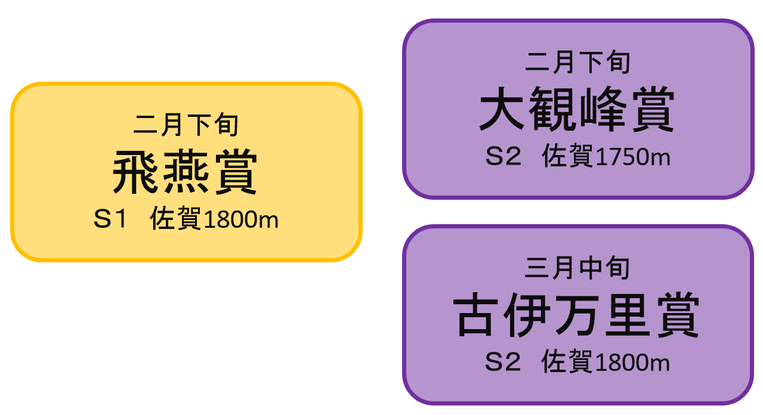

![[ウマ娘]競馬からウマ娘、ウマ娘から競馬へ。4人の『ウマ娘』ファンに魅力をインタビュー!](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/03/Er_bxjWW8AAHIIp-150x150.jpeg)

