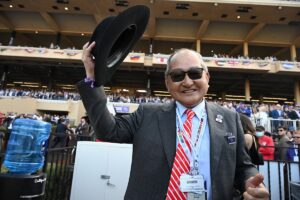1.世紀の「芦毛対決」
2025年4月から放送されているアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』。第1クールの最終話では、主人公オグリキャップと好敵手タマモクロスが初めて激突した天皇賞(秋)の決着が描かれた。カサマツから中央に移籍して破竹の重賞6連勝で天皇賞に出走したクラシック級のオグリキャップと、天皇賞(春)・宝塚記念とGⅠを連勝して秋の盾奪取に挑むシニア級のタマモクロスによる「芦毛対決」は、タマモクロスの勝利に終わる。互いの強さを認めた2人は再戦を約束して絆を深めた。
このレースのモチーフとなったのは、1988年10月30日に行なわれた天皇賞(秋)。オグリキャップとタマモクロスの初対戦となったこと、タマモクロスが勝利したことは『シンデレラグレイ』で描かれた通りである。1988年と言えば日本はバブル景気の只中。一方で秋からは昭和天皇の容態急変による自粛ムードも始まり、時代の変わり目を予感させる年とも言えた。「昭和最後の天皇賞」となったこのレースに、競馬ファンの変化を感じ取った人物がいた。作家の古井由吉である。
2.古井由吉と競馬
古井由吉と言えば、芥川龍之介賞や谷崎潤一郎賞、川端康成文学賞など数々の受賞歴を持つ、日本を代表する小説家の一人である。政治的イデオロギーを脱して人間の内面世界を鋭く掘り下げた「内向の世代」を代表する作家とされ、2020年に世を去るまで様々な作品を世に送り出した。
一方で古井は競馬エッセイストとしての顔も持っていた。JRAの機関誌『優駿』に1986年4月号から連載エッセイ「こんな日もある」を寄稿。途中で「競馬徒然草」にタイトルを変えながら、連載は2019年2月号まで続いた。1986年と言えばメジロラモーヌが史上初の牝馬三冠を達成した年。2019年の年末にはコントレイルが無敗の2歳王者に輝いているから、その期間の長さが分かるだろう。
競馬エッセイストとしての古井について、作家・競馬評論家の高橋源一郎氏は次のように評する。
古井由吉は、ものすごい、「人間」についての物語を書いた。
──高橋源一郎「競馬場の人」(古井由吉『こんな日もある 競馬徒然草』講談社、2021年)より引用
そして、同時に、「人間」ではない、サラブレッドという、別の、言葉を持たない生きものについての「物語」が支配する「競馬場」でも、「物語」を書いたのである。
古井はその鋭い観察眼で、サラブレッドと人間が織りなす「競馬場」の物語を描いてきた。しかもそのエッセイの語り口は平易で、難解さは無い。だからこそ多くの人が古井の目を通して時代時代の人々と競走馬の姿を感じ取ることができる。
3.1988年10月、2つの「大一番」
天皇賞(秋)を描いた「一九八八年十月」のエッセイは、次の書き出しから始まる。
十月二十八日、金曜日、晴。
──古井由吉「一九八八年十月」(『こんな日もある 競馬徒然草』)より引用
箱崎のエアターミナルまでもどると、もう宵の六時過ぎ、今日は金曜になると思い出した。
古井は天皇賞開催日の前々日まで、海外旅行に行っていたのである。行き先は欧州。だから天皇賞の前哨戦の結果については帰り道で購入した競馬新聞で知ることになる。
毎日王冠でオグリキャップが古馬陣を一蹴したらしい。二着は、ほう、シリウスシンボリだ。オールカマーは、なんと、スズパレードが勝っているではないか。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
天皇賞(秋)の大本命は宝塚記念を快勝した4歳馬タマモクロスだったが、消耗を嫌い前哨戦をパスして直接本番に向かうローテーションだった。そんな中、毎日王冠では6歳のダービー馬シリウスシンボリが復活の兆しを見せる2着、オールカマーではシンボリルドルフと同世代・7歳馬のスズパレードが怪我からの復帰戦を勝利と、古豪の活躍も目立った。しかし、やはり「打倒タマモクロス」の最有力候補となったのは、シリウスシンボリをはじめとした強豪古馬陣を相手に毎日王冠を快勝した3歳馬オグリキャップであった。この「大一番」、結局古井は本命を決めきれずにレース当日を迎えることになる。
さて、古井の欧州旅行、目的地の一つはフランスのパリ・ロンシャン競馬場だった。「10月のロンシャン」と言えば競馬ファンにはピンと来るはずだ。そう、世界最高峰のレース・凱旋門賞を観に行ったのである。勝ったのはイタリアのトニービン。この年のジャパンカップではオグリキャップ・タマモクロスと激突することにもなる。また、その後日本で種牡馬入りし、ウイニングチケットやジャングルポケットらの父となった。ドゥラメンテの曽祖父にも当たるから、現代の日本競馬にも大きな影響を与えている優駿と言えよう。欧州中から豪華メンバーが集まった一戦であったが、27年ぶりのイタリア馬による凱旋門賞制覇という快挙を成し遂げた。
この「大一番」の観戦で古井の印象に残ったのは、観客の姿であった。
観客の表情も日本の競馬場とずいぶん違う。大衆席では陽気にはしゃいでいる連中も見える。ビールや喰い物を沢山持ちこんで上機嫌のグループも見える。しかし、馬券ははずれる方が多いことは東西変らぬはずなのに、あのにがにがしい恨みや悔いの顔にはついぞお目にかからないのだ。さらに、身なりをよくよく観察すれば、地味は地味なり、ラフはラフなり、分に応じて、それぞれ少々ずつ洒落こんでいる。そんな観客たちが、これはどこの富豪か王侯かと目を瞠らせる豪勢なファッションの紳士淑女たちと、ごく自然に往き交っている。物欲しげでもない。目に険もない。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
日本ではハイセイコーが作り出したブームによって競馬が国民的娯楽として定着したとは言え、あくまでも「ギャンブル」という枠組みで捉えられていたのだろう。だから馬券が的中しなければ恨みがましい顔になり、外れが続けば目も険しくなる。
一方、凱旋門賞デーのロンシャンで古井は、勝っても負けても陽気に楽しむ観客たちの姿を見た。日本の競馬場との雰囲気の差に、新鮮さを感じたのだと思われる。古井は後段で競馬場の入場料が40フランであると言及した上で、このようにコメントする。
芝居の切符と考えればよいか。シャンゼリゼーの映画館の入場料よりは高い。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
競馬場を劇場や映画館と比較しているところに、古井の考え方がうかがえる。馬券の的中を目的とする「ギャンブル」ではなく、一つの「ドラマ」として競馬を捉える。そういうファンの姿を古井は目撃したのである。
そして帰国後古井が目にした最初の国内GⅠが天皇賞(秋)であった。この「大一番」、古井はどのように見たのだろうか。

4.「芦毛対決」が生み出した日本競馬の変化
レース当日の東京競馬場の様子を、古井は次のように描写する。
十月三十日、日曜日、晴。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
天気晴朗、大勢の客が東京競馬場に集まった。それにしては、場内、静かだった。オグリキャップ対タマモクロスの大一番、マスコミはさほど騒ぎ立てない。しかし競馬好きにとっては、これほど興味を掻き立てるレースもない。ほんとうに好きな客が集まったのだろう。
「場内、静か」というのは後の「オグリキャップブーム」を知る身としては意外な光景である。
まだこの時オグリキャップは社会現象と言えるほどの存在ではなかった。しかし連勝中の芦毛馬2頭の初対決は、古井を含めた競馬ファンにとって心躍るものだっただろう。「ほんとうに好きな客」だけがこのレースの価値を知っていた。
古井はパドックを見て、タマモクロスを本命に決める。しかし、自分の馬券哲学に反する買い方をするのである。
パドック三周目あたりで、タマモクロスを取ることになった。あくまでも印象の上だが、厚みが違う。オグリキャップより四十キロも軽いのに、そう見えた。もっと単純に言えば、次第に馬に見惚れたということだ。しかしオグリキャップの素晴らしさ、これを馬券の外へ切り捨てるのは忍びない。そこで一・六を買った。本線である。二百円台の馬券を本線で買うのは、私にとって、これが初めてではないか。かのテンポイントとトウショウボーイの有馬記念ですら、私は二度にわたって、この組合せを蹴っているのだ。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
タマモクロスとオグリキャップの組み合わせではオッズがつかないことを承知で、古井は馬券を購入する。これまで幾多の名勝負を見届けてきた古井も、このレースには何か違うものを感じたのだろう。
レースは古井の予想通り、タマモクロスがオグリキャップを上回る走りを見せた。観客をアッと言わせた先行策から逃げたレジェンドテイオーを捕らえ、凄まじい末脚でまくってくるオグリキャップの追撃を凌いでゴール。GⅠ3勝目を飾り、史上初の天皇賞春秋連覇を達成した。「芦毛対決」で現役最強を改めて証明した形であるが、古井が注目したのはレース後の観客の反応である。
勝ってもどって来たタマモクロスにたいして、観客の拍手は熱烈なばかりでなく、なにかきわめて歯切れのよい、冴えた響きがあった。
──古井由吉「一九八八年十月」より引用
「芦毛対決」が注目されたこのレース、勿論オグリキャップの単勝馬券を握りしめていたファンは数多かっただろうし、伏兵馬の一角崩しを予想していた馬券師たちも多かったはずだ。しかし、観客は勝利したタマモクロスを熱烈に迎えた。古井はその音が「歯切れのよい」ものだったと書き記す。それはこれまで古井が見てきた「にがにがしい恨みや悔いの顔」とは異なる姿だったと言えるだろう。
馬券の的中はひとまず置いておいて勝者を讃え、レースを楽しむ観客の姿は、古井がロンシャンで目にした光景と重なる。勝ったタマモクロスは父シービークロスを継ぐ「白い稲妻」の異名や生産牧場が倒産の憂き目に合うという境遇など、非常にドラマティックな馬だった。敗れたオグリキャップも、笠松競馬から中央競馬に乗り込んで快進撃を見せる成り上がりのドラマが人気を呼んだ。この2頭の対決という構図が実現したからこそ、このレースは「ドラマ」として捉えられたのかも知れない。競馬を「ギャンブル」ではなく「ドラマ」と見做す、その変わり目が昭和最後の天皇賞だったのではないか。

古井が目撃した日本競馬の「変わり目」は、その後大きなうねりを生む。オグリキャップとライバルたちの激闘は、日本中を巻き込むムーブメントとなる。「ほんとうに好きな客」だけが集う競馬場がカップルやファミリーのレジャースポットとしても楽しまれるようになった。また、『ダービースタリオン』や『ウイニングポスト』等の競馬ゲームが流行し、『風のシルフィード』や『みどりのマキバオー』といった競馬漫画が少年誌で連載されるなど、幅広い年代に競馬の魅力が広がっていった。
こうした競馬を「ギャンブル」ではなく「ドラマ」とみなす考え方の一つの到達点として、『ウマ娘』というコンテンツは捉えられるだろう。昭和から平成へと時代が移ろう中、競馬という娯楽の立ち位置さえも大きく変えたオグリキャップの存在は、現在に至るまで大きな影響を与えている。その端緒は、1988年の天皇賞(秋)にあった。

![[有馬記念]イクイノックスという「天才」が教えてくれたこと](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/12/img_5464-150x150.jpg)


![[随想]寺山修司のエッセイ「片目のジャック」と、片目のサラブレッド「福ちゃん」](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/08/2025081801-150x150.jpg)