![[有馬記念]思い出の2007年有馬記念。異能の馬マツリダゴッホが見せた、乾坤一擲のレース運び。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/12/Q5dvVU-2.jpg)
競馬ファンの中では、しばしばちょっとした〝論争〟のようになるネタがある。代表的なひとつに〝ダービー派〟vs〝有馬記念派〟が挙げられる。〝論争〟というと難しく考えがちだが、要はどちらのレースを好むのか、いや愛するか、といったような話だ。
自分がどちら派であるか、という話はさておくとして、ダービーが「一生に一度の大舞台でのドラマ」であることに対し、有馬記念は「さまざまな経験を積んだ馬達の生き様が織りなすドラマ」である。そのどちらに競馬の魅力、醍醐味を感じるのか。それは単なる競馬観にとどまらず、その人の人生観にも関わりそうで、だからこそ〝論争〟に発展しやすいのだろう、と思う。
上に挙げた〝ドラマ性〟の考察とは別に、レースの質を言うなら、有馬記念は自然発生的にではなく人為的に作られたもので、そこには競馬の興行面が意識されているのは間違いない。ファン投票で出走馬を選ぶ、というのは画期的だったというが、優勝劣敗の原則がベースにある競馬に取り入れるには正直、無理のあるアイデアにも思える。発案者(有馬頼寧氏)がもともと競馬畑の人ではなかったからこその着想だったかもしれないが、この案が受け入れられた背景には、「そんな発想があったのか」という〝コロンブスの卵〟的な驚き半分と、戦後復興期の高揚感とがマッチした側面があったのではないだろうか。
ともあれ、そういう〝性格〟のレースだから、「年間最強馬決定戦」という性質が生まれて当然だろう。そこがダービーとは決定的に違うところと言っていい。
一方、〝ファン投票〟で出走馬が決まる以上、「チャンピオンシップから外れている」という印象が生じることは否めない。つまり「最強馬決定戦」であるようでいて、そうでない可能性を常に秘めている、というややこしい性質を持っている。
それだけに、興味をそそられる。
そもそもシーズンオフと言っていい年の瀬に、しかも特異と言っていいコース形態の中山競馬場で、しかも根幹距離ではない2500mで争われることからして、荒れる要素が〝お膳立て〟として用意されているようなもの。ジャパンCの創設に端を発した国際化の流れによって、益々「最強馬決定戦」を謳うことが難しくなりつつある現在、「様々なキャリアを積んだ馬達の織りなすドラマ」の質も変容しつつあるのかもしれない。
そんなようなことを強烈に感じさせてくれたのが、日本が国際セリ名簿基準委員会の格付けによるパートⅠ国に昇格した2007年の有馬記念だったように思う。勝ち馬はマツリダゴッホである。
マツリダゴッホはデビュー前の調教から目立つ動きをしていて、札幌の新馬戦を7馬身差の圧勝。3戦目に2勝目を挙げ、青葉賞4着。3歳暮れのクリスマスC勝ちでオープン入りを果たすと、AJCCで重賞初制覇。秋に入ってオールカマーを制し、天皇賞(秋)15着。そこから向かったのが第52回の有馬記念だった。
何しろメンバーは揃っていた。春秋の天皇賞を制覇したメイショウサムソン、ジャパンC2着ポップロック、春秋のマイルGⅠを連覇ダイワメジャーの古馬勢に、上がり馬ロックドゥカンプ、そしてウオッカ、ダイワスカーレットの世代最強牝馬2頭。これらを相手に回しては、実績面でも勢いでも見劣ってしまう。15頭立て9番人気の低評価もやむを得ないところではあった。
ところが、蓋を開けてみると、まったく想像できなかった景色が待っていた。チョウサンが逃げて、それをダイワスカーレット、ダイワメジャーの兄妹が追い掛けるのは大方の予想通りだったが、好位のインをピッタリ進んだマツリダゴッホが、4角最内から一気にスパートして先頭に躍り出たのだ。両ダイワは後続の仕掛けどころを警戒しながら脚をタメていたし、後続は後続でタイミングを図りながらの追走だった。そこを見事に出し抜いた。上がり36秒3は最速。結果として、平均ペースで上がりも適度にかかったから、まさに乾坤一擲のレース運び。小回りの中山2500mで、シーズンをフルに走り続けてきた実績馬を相手に、いかにして戦うかを見せつけられたように感たものだ。そして、しまったなあ……とも感じた。

この「しまったなあ」こそ、特に思い出深い有馬記念として、この年のレースが脳裏に刻まれている原因になっている。しかも、その「しまったなあ」は2つある。
まずひとつ目。この年の春。マツリダゴッホを管理する国枝調教師に話を聞く機会があった。NHKマイルCを勝ったピンクカメオが本題だったが、ジックリ話を聞くのはほとんど初めてだったので、ひと通り話を聞いた後で、ちょっと脇道に逸れる格好で、それまでの師のキャリアの〝不思議〟について聞いてみた。その時点の師は開業18年目で、通算400勝を超えたところ。NHKマイルCのピンクカメオでGⅠ勝利は3個目。通算の重賞勝利数は9個目だった。
「少ないって? そうなんだよなあ」
とバツが悪そうに、でも苦笑しながらも丁寧に、真面目に応えてくださった。
「でも、やっとだけど、ここにきていい感じで馬も揃ってきたから、もうちょっといい結果が出せるようになると思うんだ」
その夏にクーヴェルチュールでキーンランドCを、秋になってマツリダゴッホのオールカマー、マイネルシーガルの富士Sと重賞を3勝。そうして迎えたのが有馬記念であり、マツリダゴッホの勝利は、金子真人オーナーの持ち馬以外で初めてのGⅠ制覇だった。いやもう、まったく取材を予想にいかせなかったなあ、という「しまったなあ」があった。
そしてもうひとつ。実はこの年、競馬場で配られるレーシングプログラムの巻頭コラムを書かせてもらっていた。初回がダービー号で、この有馬記念号も担当した。その文中では出走予定の有力馬を何頭か紹介するようにしていたのだが、マツリダゴッホの名前はどこにも出てこない。こっちの方でも、まったく春の取材をいかせなかったなあ、と……。
マツリダゴッホはその後、日経賞を制し、オールカマーは3連覇を達成。中山では通算13戦8勝、うちGⅠ1勝、GⅡ5勝という無類の巧者ぶりを見せる。一方、左回りでは馬券の対象にすらなったことがないのだから、それは〝異能〟と言っていい才能だったかもしれない。有馬記念はそういう特異な一面も覗かせる。また、この時の有馬で手綱を取った蛯名騎手と国枝師のコンビは、3年後のアパパネの快挙の物語にもつながっていく。
有馬記念というレースは、確かに個々のサラブレッドが歩んできた道程、経験が織りなすドラマには違いない。それが極上のものなのか、そうでないのかは、観る側の受け取り方にかかっている。とすれば、どうやら冒頭に書いた通り、観る側の人生観も問われるレース、ということになるのかもしれない。
写真:RINOT



![[有馬記念]思い出の2007年有馬記念。異能の馬マツリダゴッホが見せた、乾坤一擲のレース運び。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/12/Q5dvVU-2-150x150.jpg)
![[中山大障害]3歳で"天下"統一。障害キャリア3戦でJ・G1を勝った天才ジャンパー、テイエムドラゴン。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/12/CXEQL62UsAASJ5o-300x199.jpeg)
![[有馬記念]今も駆ける スター"ウマ娘"の血を引く者たち〜日曜重賞編〜](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/04/e3defdd4ecd-300x100.png)
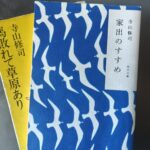
![[エッセイ]「また、会いたいな」。白い奇跡が織りなす夢物語](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/08/2025081403-150x150.jpg)





