
北海道を訪れる多くの人が利用する、新千歳空港。
その地に降り立ち、空を見上げると、サラブレッドを愛する者にとっては、ある種の情感が呼び起こされる。
かの名馬たちも、同じ空を見上げていたのか、と。
かつてその空には、あたりに生息していた、多くの鶴が舞っていた。
そのことから、「鶴は千年、亀は万年」の故事にちなみ、この地は「千歳」と名付けられたという。
また、「千歳」という語には、「幸せな人生を、末永く生きられますように」といった意味を持つとされる。
そうした由来や語義も、さることながら。
「千歳」とは実に、美しい響きを持つ言葉である。
その美しい言葉を、耳にすると。
ふと、その名を冠したサラブレッドのことを、思いだす。
サクラチトセオー。
桜色の勝負服を纏った、小島太騎手との名コンビ。
そして何より、「千歳」の名にふさわしく、末永く、それでいて豪快な末脚を持つ優駿だった。

1995年10月29日、天皇賞・秋。
当時6歳だったサクラチトセオーは、2番人気に支持されていた。
しかし、戦前から話題を集めていたのは、2頭のサラブレッドの出走だった。
1番人気を集めた、ナリタブライアン。
前年の1994年に牡馬クラシック三冠に輝き、初めて古馬相手となったグランプリ、有馬記念も制覇、年度代表馬の栄誉にも浴した。
しかし、明けて5歳の始動戦となったGⅡ阪神大賞典を7馬身差で圧勝し、孤高の覇道を突き進むものと思われた矢先、股関節炎を発症してしまい、春シーズンを休養。
その復帰戦となったのが、この天皇賞・秋だった。
2022年の現在は、外厩制度や調教技術の発達により、GⅠに休養明けから挑むことも珍しくはなくなったが、当時はステップレースを使いながら仕上げていくローテーションが主流の時代だった。
史上5頭目の三冠馬は、久々の実戦という不利を覆せるのか、否か。
怪我は完治したのか、休養前の状態まで戻っているのか、それとも。
その揺れ動く心理の中で、ファンはこれまでの圧倒的な走りが復活することを期待して、ナリタブライアンに1番人気を託した。
出走することで注目を集めたもう一頭が、ジェニュインだった。
偉大なるサンデーサイレンスの初年度産駒として、同年の皐月賞馬を制し、ダービーでも2着と好走し、春のクラシックをにぎわせた4歳馬。
しかし、秋の三冠目・菊花賞には向かわず、この天皇賞・秋で古馬との対戦を選んだ。
当時は、春のクラシックで好走した馬は、菊花賞に向かうのが大多数。
1987年に、天皇賞・秋への4歳馬の出走が解放されていたが、この1995年までの8年間で、4歳馬の出走はわずかに3頭にとどまっていた。
クラシック登録のなかった「怪物」オグリキャップが2着に好走していたものの、その他の2頭は着外に敗れている。
栄誉ある菊花賞に出走できるのは、4歳秋の一度だけ。
まして、春のクラシックで好走するような素質馬であれば、菊花賞に向かうのが、当たり前。
しかし、そうした過去の慣習に抗い挑戦することを、松山康久調教師をはじめとする陣営は選んだ。
皐月賞と同じ距離、そして好走したダービーと同じ東京コース。
古馬との力関係と2キロ減の斤量を考慮すると、ジェニュインならば勝負になるだろうという目算が、陣営にはあったのだろう。
新しい世界の扉を開かんと挑んだジェニュインは、4番人気に支持されていた。
翻って、サクラチトセオー。
日本競馬の歴史において、数々の名馬の名に刻まれた「サクラ」の冠。
境勝太郎調教師、小島太騎手、そして馬主・さくらコマースが織りなす円環は、サクラショウリ、サクラユタカオー、サクラチヨノオー、あるいはサクラバクシンオーといった名馬で大レースを制してきた。
チトセオーもまた、当時の「チーム・サクラ」のなかの、期待馬だった。
デビューから素質の高さは折り紙つきだったが、腰の状態が万全ではなく、体調面と相談しながらの調教、レース選択を強いられてきた。
そんな中でも、世代の頂点を決める日本ダービーに出走し、古馬となっては格上挑戦でGⅡ中山記念を制し、あるいはGⅢ京王杯オータムHをレコード勝ちするなど、その才能の片鱗は随所に見せていた。
追うほどに伸びる豪快な末脚と大レース向きの底力は、父・トニービンから多くの産駒が受け継いでいた資質でもあった。
この1995年、6歳となったサクラチトセオーだったが、春の安田記念でハートレイクの2着、続く宝塚記念はダンツシアトルの7着と、悲願のGⅠタイトルになかなか届かない走りが続いていた。
前哨戦のGⅡ毎日王冠は、逃げたスガノオージを捉えきれずの4着。
折しもこの秋、小島太騎手は翌1996年で騎手を引退し、調教師に転身する予定を発表。
堺勝太郎調教師もまた、定年まで残り1年と4か月ほどになっていた。
日本競馬を彩ってきた、「サクラ」の円環。
その形が、徐々に変わりゆく時期でもあった。
残された時間、そしてチャンスは、それほど多くはない。
そういった意味で、1995年の天皇賞・秋が、サクラチトセオーの陣営にとって大きな意味を持っていたことは、想像に難くない。
分厚い雲が秋空を覆う下、「秋の盾」をめぐるファンファーレが鳴り響く。
この日の東京競馬場には18万人を超えるファンが詰めかけ、天皇賞・秋としての入場人員レコードを更新。
その大観衆の視線が、一点に集中する。
難しい東京2000mのスタート、17頭がゲートから飛び出す。
好枠の4番枠からジェニュインが出るが、その外のトーヨーリファールが先手を取り、2コーナーに向かう。
不利な17番枠からのスタートとなったスガノオージは、押して挽回していく。
その後ろにアイルトンシンボリ、ホクトベガあたりが先団を形成。
そして、6、7番手あたりの好位で、ナリタブライアンの白いシャドーロールが揺れている。
最内1番枠からの発進のサクラチトセオーだったが、慌てず騒がずといった風情で、いつものように後方2番手を単独で追走。
向こう正面に入り隊列が固まり、淡々とレースは流れていく。
トーヨーリファールが軽快に逃げて、3コーナーの大欅を過ぎる。
ジェニュインも変わらず、内の2番手で岡部幸雄騎手が手綱を絞っている。
的場均騎手が、ナリタブライアンを少しずつ外に持ち出し、じりじりと押し上げていこうとしている。
サクラチトセオーは、そのはるか後方から、徐々に大外から進出していく。
17頭が横に広がり、死力を尽くした直線の攻防。
馬場の真ん中にエスコートされたナリタブライアンだが、的場騎手の手綱の動きとはうらはらに、伸びてこない。
馬群の中でもがく、黒鹿毛。
復活は、成らず。
しかし、揺れる白いシャドーロールを、いつまで見つめているわけにもいかない。
前に視線を移すと、トーヨーリファールがまだ粘っている。
それを交わさんとジェニュインが迫る。
内からはマチカネタンホイザ、そしてアイルトンシンボリも脚を伸ばす。
そして大外から、ピンクの勝負服。
小島太騎手の豪快なアクションに応え、前との差を詰めていく。
その脚にはどこか、重さと力強さが混在していた。
残り100mのハロン棒を通過したところで、ジェニュインが前に出る。
外からサクラチトセオー。
鬼気迫る勢いで追う、小島太騎手。
ゴールまでの残りの距離と、2頭の脚色。
そこからはじき出された目算は、「届かない」。
初の4歳馬の戴冠、偉業達成か。
そう思われた、ラスト数十メートル。
府中の坂を登り切り、死力を尽くしたその剣が峰で、サクラチトセオーは弾けた。
それまでの重さを振り払うかのように、しかし、力強く伸びた。
並んだ、内と外の馬体。
ジェニュインと馬体を並べたところが、ゴール板だった。
差したのか、残したのか。
18万人のどよめきが、レースの余韻のように府中を包んでいた。
写真判定ののち、一番上に灯った「1」の馬番。
サクラチトセオー、1着。
史上初の4歳での天皇賞・秋制覇を狙ったジェニュインと岡部騎手は、非の打ちどころのないレース運びをした。
しかし、その快挙が成るその寸前に、サクラチトセオーの豪脚が、わずかにハナ差で秋の盾を攫っていった。
ついにGⅠのタイトルに届いた、チトセオーの末脚。
上がり3ハロン34秒3は、出走馬中1位。
後方待機から、直線だけで14頭を抜き去った。
「あんなに追ったのは何十年ぶりだよ」と、当時48歳の小島太騎手はおどけてみせた。
管理する境勝太郎調教師も、「わたしが長い人生で泣いたのはチヨノオーのダービーに次いで2回目のことです」と喜びを表現する。
この「サクラ」の円環は、2週間後のエリザベス女王杯でも、チトセオーの半妹であるサクラキャンドルで戴冠。
日ごと引退が近づく中、小島太騎手の手綱と「サクラ」の勝負服は、どこか特別な光を纏っていた。
時に、1995年。
移りゆく時代、変わりゆく「サクラ」の円環のかたち。
その中で、サクラチトセオーと小島太騎手は、秋の天皇賞でひときわ強い輝きを放った。
「末永く、幸せな人生を生きられますように」
「千歳」の語の持つ、その祈り。
そのことばを耳にすると、あの天皇賞・秋を思い出す。
「千歳」の名の通り、末永く、それでいて豪快な、あの豪脚。
サクラチトセオー。
「桜」と「千歳」という、美しい名を冠した、天皇賞馬である。

写真:かず





![[天皇賞・秋]G1レース直前プレビュー](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/11/bFZ-bgsv-300x200.jpg)
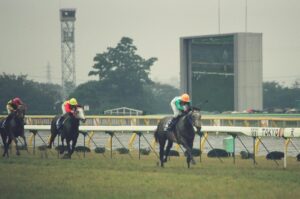


![[ウマ娘]ひときわ大きなウマ娘! ウマ娘ヒシアケボノと、史実馬ヒシアケボノ。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/10/bandicam-2021-10-03-01-15-54-283-150x150.jpg)
![[南部杯]トウケイニセイにメイセイオペラ、トーホウエンペラー…。岩手の伝統JpnⅠを制した名馬たち。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/02/4F349670-D847-4A76-A6EB-304B3A921E50-150x150.jpeg)



